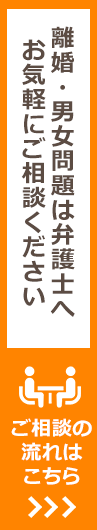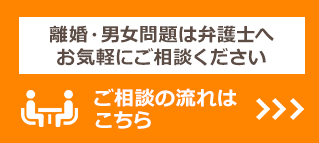離婚裁判とは
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に離婚を求める側が、家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判所の判決によって離婚する事です。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれます。
裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しない場合であっても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。
まずは調停での話し合いが必要
すぐに離婚訴訟を起こすことができるわけではなく、まずは調停で話し合う必要があります。原則として、調停で解決することができず、不成立(または取下げ)で終了した場合に、離婚訴訟を提起することができるのです。これを調停前置主義といいます。
裁判所が離婚を命じるためには法定の離婚事由(離婚原因)が必要
裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。
離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。
不貞行為
自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性交渉を行うこと場合です(いわゆる浮気や不倫の行為)。性交渉が一時的なものか継続しているか、愛情が有るか無いかは関係ありません。
悪意の遺棄
同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、正当な理由なく、履行しない場合です。
3年以上の生死不明
3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶え、生死不明な場合です。生死不明が7年以上に及ぶ場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされて離婚が成立します。
回復の見込みがない強度の精神病
その精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務を十分に果たすことのできない程度に達している場合です。
ただし、配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
社会通念からみて配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎるといわねばならないほど婚姻関係が破壊された場合です。
婚姻を継続しがたい重大な事由は、性格の不一致、夫婦双方の意思、言動、信頼関係の破壊の程度、交流の有無、同居の義務、子どもの年齢、子どもの意思などの事情から、裁判所が判断します。
一例として、配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役などがあります。
離婚裁判の流れ
①家庭裁判所に訴訟提起をする
裁判所に離婚の裁判をしてもらうためには、必要な書類を裁判所へ提出しなければなりません。最低限、以下の書類を準備する必要があります。
・訴状
当事者の情報や離婚に至る事情、法定の離婚事由があることなどをまとめた書面です。
・調停不成立等証明書
調停を行った裁判所に所定の申請書を提出することで、調停が不成立等で終了したことを証明する書面を発行してもらえます。
・戸籍謄本
②裁判手続きの開始
裁判を起こした側を「原告」、裁判を起こされた側を「被告」といいます。
裁判所は、原告から提出された書面をチェックし、第1回期日の日時を設定した上で、被告に対して「訴状」等の書類を送付します。その中に「答弁書」の書式も同封されています。
被告は第1回期日までにこの「答弁書」を提出しなければなりません。
③第1回期日(口頭弁論)
第1回期日は、少なくとも原告側は裁判所へ出席する必要があります。弁護士に依頼している場合は、弁護士が出席すれば足りますので、原告本人の出席は不要です。
被告側は必要事項を記載した答弁書を提出することで、第1回は欠席することができます。
被告側が書面を何も提出せずに第1回期日を欠席した場合には、裁判所は原告側の請求を全て認める判決を出します。
その場合を除き、通常、1回で裁判が終わることはほとんどありませんので、次回期日を設定し、第1回は終了します。裁判は1か月に1回程度のペースで開催されます
④主張・反論、争点整理を行う
原告と被告は、互いに書面で、自分たちの主張を行い、また、相手の主張に対して反論を行います。そして、必要な証拠は適切なタイミングで提出していくことが重要です。
裁判官は、原告と被告の主張を踏まえて、どういった点で主張が対立しているのかなどを整理しながら審理を進めていきます。
⑤尋問
原告と被告の主張反論がおおむね出そろった段階で、必要な範囲で証人(本人)尋問を行います。
裁判官の面前で、裁判所の審理に必要な事柄について述べる必要があります。
⑥離婚裁判の判決言い渡し
裁判所は審理の内容をふまえて、判決を出します。
原告の離婚請求を認める判決がだされると、その判決によって当事者は法律上離婚したことになります。
他方で、原告の請求が認められず、棄却されると、婚姻関係が維持されることになります。
⑦和解の打診について
「裁判」というと、裁判官の判決によって終わるイメージをもたれる方が多いかもしれませんが、話し合いで解決することも多くあります。その多くは、裁判所から「こういう内容で和解しませんか」と打診される場合があります。
双方あるいは片方の当事者がこの和解案に納得ができない場合は、判決で終了することになります。
離婚裁判の期間
訴訟を提起し、判決がでるまでの期間は、裁判所が公表しているデータをもとにしても、平均して1年6か月以上かかります。親権が争われる場合にはより長期化する傾向にあるといえるでしょう。
判決確定後の流れ
判決がでて双方が控訴をしなかった場合、判決の内容が確定し、争うことができなくなります。
離婚が成立した場合は、判決が確定した日を含めて10日以内に役所へ届出が必要です。相手方の署名押印は不要です。新潟市の場合は以下の書類を提出しなければなりません(新潟市HPより)。
・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通 ※本籍地の市区町村へ届出る場合は不要です
・判決書の謄本
・判決の確定証明書
・本人確認書類
判決の内容に納得できない場合
裁判所の出した判決の内容に不服がある場合は、控訴という手続きをとり、争うことができます。
この控訴ができる期間は、判決文を受け取った日の翌日から14日が満了するまでの間に「控訴状」等必要な書類を裁判所に提出しなければなりません。
また、控訴した後50日以内に、「控訴理由書」を高等裁判所に提出しなければなりません。
たとえば、新潟家庭裁判所で判決が出た場合、控訴状は新潟家庭裁判所に提出をし、控訴理由書は東京高等裁判所に提出することになります。
弁護士をつけずに自分で離婚裁判を行う場合
裁判は弁護士をつけなくとも訴訟提起することができますし、裁判所へ出席することもできます。
この場合、当然、弁護士費用は発生しませんので、裁判所に納める以下の手数料の負担で済みます(以下の手数料のほか、戸籍謄本を役所から取得する際の手数料がかかります)。
収入印紙代:13,000円
※離婚と併せて慰謝料請求をする場合は請求額に応じて追加の印紙代が発生します。
郵便切手代:裁判所によって裁判所へ納める郵便切手代が異なります。
附帯処分(養育費や財産分与・年金分割):1件につき1,200円
弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。当事務所の弁護士費用についてはこちらのページをご覧ください
離婚裁判を弁護士に依頼した方良い理由
①離婚裁判を有利に進めることができる
離婚裁判で自分に有利に進めるためには、裁判官にご自身の主張を理解してもらうことが重要です。そのためには、まず説得力ある書面を作成しなければなりません。この書面の内容は、法律論を組み立て、本件に必要な裁判例を正確に引用し、事実関係をきちんと整理をして記載しなければなりません。これをご自身でやろうとするのは至難の業といえます。弁護士に依頼することで、これまでの経験等をもとに、裁判官に納得してもらえる内容の書面を作成し、提出することができます。
また、裁判官は証拠をとても重要視します。だからといって、なんでもかんでも証拠として選択肢、大量に出せばよいというものではありません。弁護士に依頼することで、どういった証拠が効果的であるのかを検討した上で、必要な証拠をピックアップし、裁判所に提出することができます。
②精神的な負担を軽減することができる
離婚裁判は上述のように平均して1年6か月以上の期間がかかります。このような長期間、お仕事や家事をしながら、専門家のサポートなくお一人だけで訴訟を続けることは、精神的に非常に負担です。弁護士に依頼することで、専門的な書面の作成や裁判所への出廷を任せることができ、その負担が大幅に軽減されます。
裁判離婚の注意点
裁判離婚では、原則として、離婚原因を作った有責配偶者から離婚訴訟を行うことができません。例えば浮気相手と結婚したいがために、浮気をした夫から妻に対して、離婚を請求することはできません。
しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。
・別居期間が同居期間と比較し、相当長い
・未成熟の子ども(親から独立して生計を営むことができない子ども)がいない
・離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない
ただし、条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。このように、有責配偶者からの訴訟が認められるようになった理由は、婚姻観・離婚観が時代によって変化する中で、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが考えられるようになったからです。